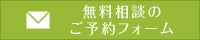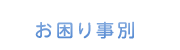遺留分権の内容が変わりました
遺留分についての請求の方法や内容が大きく変わったと言われていますが、どのように変わったのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
これまでの遺留分制度
例えば、父親が死亡して相続人が長男Aさん、二男Bさんの2人だけだったとします。
このとき、父親が「Aさんに財産の全部を相続させる」という遺言を残して死亡したとします。
遺言は有効なのですが、そのままではAさんとBさんの間に大きな不公平が生じますし、Bさんが生活に困ってしまうのでは社会的に見ても不適切です。
そこで、Bさんには、一定の割合(この例では4分の1)で遺留分という権利が認められ、それをAさんに対して請求していくことができます。
これまでの民法で定められていた遺留分に関する請求権は遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)という形でした。
「減殺(げんさい)」はあまり使わない言葉ですね。
旧法では、「遺留分減殺請求により、遺言などによる財産移転の効果が失われる」という定めだったため、その法的な性質を正確に表すために「減殺」という用語を使っていました。
しかし、そのような定め方では色々と不都合が生じるため、民法の相続分野を改正するにあたって、実態に即して制度の内容を変えました(民法1046条)。
権利の法的な性質を変えました
以前の遺留分減殺請求権によると、どのような不都合が生じるのでしょうか?
さきほど書いた具体例で考えてみましょう。
【例①】父親が長男Aと同居していた自宅の土地・建物と預金を残していた場合。
ここでBさんが遺留分減殺請求を行うと、自宅土地・建物と預金の4分の1が当然にBさんのものとなります。
つまり、Bさんが遺留分減殺請求により、父親の遺言によるAさんへの財産の移転の効果が失われるという効果が生じます。
Aさんは、お金で解決したいという主張(価額弁償の抗弁)をすることはできますが、Bさんからはそれができませんでした。
【例②】父親がAさんと一緒に事業を行っていて、事業用の資産として土地・建物や株式をAさんが引き継いだ場合。
ここで、Aさんが4分の1のお金をすぐに支払えないときに、Bさんが意地になって事業用資産の4分の1を主張すると事業の経営自体がうまく引き継げません。
これでは、相続の争いにより、従業員や取引先にも迷惑をかけてしまうことになりかねません。
そこで、改正法では、遺留分の権利はあくまでお金を請求する権利であり、財産に対して直接関与できる権利ではないと定めました。
そこで、「減殺」という用語も廃止して、「遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)」という名称に一新しました。
改正後では、Bさんは、遺産の4分の1の金銭を請求できますが、Aさんが引き継いだ土地・建物などについては直接の権利を持たないとしたのです。
これによって、遺留分による相続の問題をより円滑に進められるようにしたのです。
侵害額を支払えないとき
上の例で、AさんがBさんの請求する遺留分侵害額をすぐに支払えれば問題ありません。
しかし、次のような場合も珍しくないでしょう。
- 自宅の土地・建物と預貯金を相続したけれど、預貯金の額が少なくて、遺産の4分の1にはとても届かないとき。
- 父親の遺産のほとんどが事業用財産であり、遺産から支払えるお金がほとんどないとき。
このような場合に、すぐに遺留分侵害額を支払えと請求されてもAさんは困ってしまいます。
そこで、Aさんのような受遺者や生前贈与を受けた相続人は、裁判所に対して金銭の支払いについて全部又は一部について、相当の期限の許与を求めることができるとしました(民法1047条5項)。
これにより、Aさんがお金を調達するだけの余裕ができるため、相続財産の一部を換金して用意したり、事業収入により分割払いをしたりすることができます。
Bさんは、すぐにお金を欲しいかもしれませんが、そのためには強制執行をしなければならず、お金もかかりますし、新たな紛争続くことになります。
そうであれば、裁判所が決めた期限をAさんが守ってくれて、しっかりとした期限の中で支払いを受けた方が、長い目で見れば得なことということになります。
全体として、今回の遺留分制度の改正は、遺留分についての争いを現実的・円滑に解決しようとして行われていると言えるでしょう。
施行された時期
改正法は2019(令和元)年7月1日(施行日)以降に生じた相続から適用されます。
被相続人(上の例では父親)が亡くなった時期が施行日以降かどうかで判断するため、遺言が書かれたり、生前贈与がされたのが施行日前でも、亡くなったのが施行日以降であれば、新法が適用されます。
- 遺留分権の内容が変わりました
- 相続人ではない妻や兄弟の介護の努力は認められるの?
- 結婚して長くたった夫婦の間での贈与は戻さなくていいの?
- 夫が死亡したとき配偶者は死ぬまで自宅に住めるのでしょうか?
- 夫名義の建物に住んでいる妻には、居住権はあるのですか?
- 遺産分割前に財産処分があったときの調整方法は?
- 相続人の範囲と相続分(法定相続人)
- 連帯保証債務など債務の相続について
- 遺産を分けるときに選択する手続
- 他の相続人が遺産を勝手に処分するかも!?
- 行方が分からず生死不明な人の相続手続
- 【遺産分割調停】 遺産争いで話がまとまらない
- 遺産分割の対象となる財産は?
- 相続権を失ってしまう場合(相続欠格)
- 遺産分割調停や審判での預貯金の取り扱い
- 寄与分が認められるのはどんなとき?
- 特別受益の意味と計算の方法
- 安心できる遺言の書き方は?
- 遺言はどのような方法でやるの?
- 自分で遺言を書きたい場合
- 自分で自由に書いた遺言書は有効?
- パソコンで本文、署名が手書きの遺言は有効?
- 遺言の内容を秘密にしておきたい場合
- 遺留分って何のこと?
- 誰が先祖の供養をやっていくの?
- 分割する財産を選べる(一部分割)改正がされたと聞きましたが
- 手書きでの遺言を書きやすくするための改正
- 遺産を分ける前に預金の一部を払い戻す方法
- 遺留分権の内容が変わりました
- 相続人ではない妻や兄弟の介護の努力は認められるの?
- 結婚して長くたった夫婦の間での贈与は戻さなくていいの?
- 夫が死亡したとき配偶者は死ぬまで自宅に住めるのでしょうか?
- 夫名義の建物に住んでいる妻には、居住権はあるのですか?
- 遺産分割前に財産処分があったときの調整方法は?
- 相続人の範囲と相続分(法定相続人)
- 連帯保証債務など債務の相続について
- 遺産を分けるときに選択する手続
- 他の相続人が遺産を勝手に処分するかも!?
- 行方が分からず生死不明な人の相続手続
- 【遺産分割調停】 遺産争いで話がまとまらない
- 遺産分割の対象となる財産は?
- 相続権を失ってしまう場合(相続欠格)
- 遺産分割調停や審判での預貯金の取り扱い
- 寄与分が認められるのはどんなとき?
- 特別受益の意味と計算の方法
- 安心できる遺言の書き方は?
- 遺言はどのような方法でやるの?
- 自分で遺言を書きたい場合
- 自分で自由に書いた遺言書は有効?
- パソコンで本文、署名が手書きの遺言は有効?
- 遺言の内容を秘密にしておきたい場合
- 遺留分って何のこと?
- 誰が先祖の供養をやっていくの?
- 分割する財産を選べる(一部分割)改正がされたと聞きましたが
- 手書きでの遺言を書きやすくするための改正
- 遺産を分ける前に預金の一部を払い戻す方法