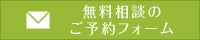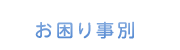自分で遺言を書きたい場合
自分で遺言を書きたいのですが、どのような方法をとれば有効なのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
自分で書く遺言を自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)と呼びます。
これは、遺言をする人自身が、その全文・日付・氏名を手書きで書き、これに印を押すという遺言です。
印鑑は実印である必要はなく、認め印(いわゆる「三文判」)でも構いません。
そして、印鑑に代わるものとして最高裁判所は、「指印」も有効としています。
これに対して「花押(かおう)」を書いたものは無効だと判断しました。
花押というのは、手書きで書いた印影に似た書体をいいます。
署名をした後に、名字や名前を有名人のサインのように崩して書くのが典型的な例です。
遺言が効力を生じるときには、書いた人は亡くなっていて意思確認ができないので、書くときに厳格な要式を意識したものだけを有効とする趣旨です。
自費津証書の用紙や形式に制限はありませんが、手書きでなければいけないので、パソコンなどで作成したものは無効になってしまいます。
本文をパソコンで書いて、自筆で署名して押印しても無効なので注意してください。
なお、財産目録等に限っては一定の条件の下にパソコンで作ることも可能です。詳しくは、こちらへ→https://www.hanamizuki-law.com/succession00007.html
自筆証書という方法は、自分だけでできるので、費用も手間もがかからないというメリットがあります。
しかし、後で「本当の意思ではなかったはず!」とか「誰かが勝手に作ったものだ!」などの争いになったり、他の相続人に隠されたり、破棄されたりしてしまう危険があります。
争いになりそうなときはもちろんですが、ご自分の相続人の間の紛争を避けるためにも公正証書で遺言を作った方が良いでしょう。
※ 相続法改正で、手続が簡単で費用も安い形で、法務局が遺言を預かってくれる制度もできました。制度の運用が固まったら、またご説明するようにしますね。
- 遺留分権の内容が変わりました
- 相続人ではない妻や兄弟の介護の努力は認められるの?
- 結婚して長くたった夫婦の間での贈与は戻さなくていいの?
- 夫が死亡したとき配偶者は死ぬまで自宅に住めるのでしょうか?
- 夫名義の建物に住んでいる妻には、居住権はあるのですか?
- 遺産分割前に財産処分があったときの調整方法は?
- 相続人の範囲と相続分(法定相続人)
- 連帯保証債務など債務の相続について
- 遺産を分けるときに選択する手続
- 他の相続人が遺産を勝手に処分するかも!?
- 行方が分からず生死不明な人の相続手続
- 【遺産分割調停】 遺産争いで話がまとまらない
- 遺産分割の対象となる財産は?
- 相続権を失ってしまう場合(相続欠格)
- 遺産分割調停や審判での預貯金の取り扱い
- 寄与分が認められるのはどんなとき?
- 特別受益の意味と計算の方法
- 安心できる遺言の書き方は?
- 遺言はどのような方法でやるの?
- 自分で遺言を書きたい場合
- 自分で自由に書いた遺言書は有効?
- パソコンで本文、署名が手書きの遺言は有効?
- 遺言の内容を秘密にしておきたい場合
- 遺留分って何のこと?
- 誰が先祖の供養をやっていくの?
- 分割する財産を選べる(一部分割)改正がされたと聞きましたが
- 手書きでの遺言を書きやすくするための改正
- 遺産を分ける前に預金の一部を払い戻す方法
- 遺留分権の内容が変わりました
- 相続人ではない妻や兄弟の介護の努力は認められるの?
- 結婚して長くたった夫婦の間での贈与は戻さなくていいの?
- 夫が死亡したとき配偶者は死ぬまで自宅に住めるのでしょうか?
- 夫名義の建物に住んでいる妻には、居住権はあるのですか?
- 遺産分割前に財産処分があったときの調整方法は?
- 相続人の範囲と相続分(法定相続人)
- 連帯保証債務など債務の相続について
- 遺産を分けるときに選択する手続
- 他の相続人が遺産を勝手に処分するかも!?
- 行方が分からず生死不明な人の相続手続
- 【遺産分割調停】 遺産争いで話がまとまらない
- 遺産分割の対象となる財産は?
- 相続権を失ってしまう場合(相続欠格)
- 遺産分割調停や審判での預貯金の取り扱い
- 寄与分が認められるのはどんなとき?
- 特別受益の意味と計算の方法
- 安心できる遺言の書き方は?
- 遺言はどのような方法でやるの?
- 自分で遺言を書きたい場合
- 自分で自由に書いた遺言書は有効?
- パソコンで本文、署名が手書きの遺言は有効?
- 遺言の内容を秘密にしておきたい場合
- 遺留分って何のこと?
- 誰が先祖の供養をやっていくの?
- 分割する財産を選べる(一部分割)改正がされたと聞きましたが
- 手書きでの遺言を書きやすくするための改正
- 遺産を分ける前に預金の一部を払い戻す方法