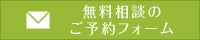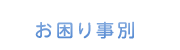証明する責任は原告にある?
訴訟を起こされて被告になってしまった場合、何を主張して証明していけば良いのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
証明責任はまずは原告が負う
民事訴訟においては、請求を支える基本的な事実関係は原告(訴えた方)が証明する責任があります。
例えば、原告が「お金を300万円を、年利7%で1年間貸したけれど返してくれない!」という貸金返還請求をするために皆さんに裁判を起こしたとします。
その場合、原告は次の5つの事実を証明していかなければなりません。
① 原告が皆さんに金銭を渡したこと(金銭の授受)
② 原告が皆さんとお金を返す合意をしたこと(返還の合意)
③ 原告が皆さんと返す期限について合意をしたこと(返済期限の合意)
④ 約束した返済期限が過ぎたこと(返済期限の到来)
⑤ 利息を7%と合意したこと(利息の合意)
なお、原告が、期限を過ぎたときに利息より高い率の損害賠償請求をする約束(遅延損害金についての合意)を主張していく場合には、上記の5つに加えて
⑥ 遅延損害金の利率についての合意
を証明していく必要があるのです。
これを「請求を基礎づける事実については、原告に証明責任がある」と言われます。
証明責任の分配とは?
何のためにこのような証明責任の分配をするのでしょうか?
裁判官も神様ではないのですから、いくら証拠を見ても、常識に照らしても「分からない」という場合があります。これを法律の慣用語でノンリケットと言います。
ノンリケットだからといって、裁判官が判決で「分かりませんでした」という判決を下してしまっては、紛争が解決しません。
そこで、もし裁判官が「分からない」と判断した時には、証明責任を負う方に「証明不十分」だとして敗訴の判決を下すことになるのです。
例えば、貸主が貸金の返還請求をしていっても、契約書がないと「金銭の授受」や「返還の合意」が証明できないことがあります。
また、お金を貸す時に銀行振込で貸したので「金銭の授受」は証明できるけれど、「返還の合意」を証明できない場合は非常に難しい争いになります。
原告は「返してもらう約束をした」と主張するのに対して、被告が「もらったものだ」(贈与)の主張をして争っていくことになります。
この場合には、原告と被告との間に、それだきの金額を贈与するだけの関係や事情があったのか、常識に照らして推論していくことになります。
それでも、贈与か貸付かの判断ができないときには、原告敗訴となるのです。
ですから、「お金を貸す」など様々な契約をする時には、しっかりと弁護士に相談して裁判で負けない証拠になるものを作る必要があるのです。
証明の程度
もし、これらの事実の証明が不十分だと普通の人が疑いを差し挟まないであろう程度の証明が必要です。
この証明は相当高いレベルです。
例えば、お金を貸した例でいうと、被告の自筆で署名・捺印した契約書に必要事項が書かれていれば原告の証明責任は果たされていると言えるでしょう。
また、契約書が無くても間接的な事実から証明できることもあります。
例えば「原告が被告名義の口座に銀行振込でお金を振り込んでいること」「その後、被告から原告名義の口座に定期的に入金があること」を銀行の取引明細で証明できれば、普通の人だったら「お金を借りたから、分割で返しているんだな」と思いますから、やはり証明ができたといえるでしょう。
どのような間接的な事実を選ぶのか?
どのような資料を探して証明していけば良いのか?
を訴訟手続をやりながら判断するのが、まさに弁護士の腕の一つといっても良いでしょう。
その意味では、「確実な証拠が少ないけれど推測の根拠となる資料は選択できる」という事件が、弁護士の腕の差が出やすい事件と言えるでしょう。