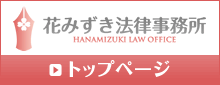師走とは良く言ったもので、12月に入ってから、色々と忙しいです。
年末で一区切りつけたいという気持ちが、人間誰しもあるようですね。
私も、難問に一区切りをつけて、年を越せればと思っています。
さて、裁判員裁判の合憲性について、引き続き考えていきたいと思います。
裁判官と裁判員とが「裁判所」として判決を下すことは、「特別裁判所」を設けたことにならないかという問題があります。
憲法76条2項は、「特別裁判所は、これを設置することはできない。」と定めています。
これは、戦前に、例えば、違法な課税処分を争う場合には、通常の司法裁判所ではなく、行政事件を特別に扱う行政裁判所が扱うこととされていました。
でも、行政が行った処分を行政機関が判断しても、適切に法律を適用して解決してくれるとは思えません。
そこで、日本国憲法は、裁判を行う権利を司法裁判所のみに持たせて、他の機関が最終的に問題を解決する手段としての裁判を行うことを禁じたんですね。
そして、司法裁判所の構成は、憲法上は裁判官によってなされるように規定されています。
とすると、裁判員が裁判を行うことは、憲法が禁じている「特別裁判所」を設けることにならないかという問題が生じるんですね。
これに対して、最高裁は次のように言って、76条2項に反しないとしました。
「特別裁判所」は、通常の司法裁判所の系列の外に置かれ、特別な事件について裁判権をする裁判所を言います。
しかし、裁判員制度による裁判体は、地方裁判所に属するもので、それに不服があれば、高等裁判所への控訴、最高裁判所への上告が認められています。
とすると、裁判員裁判は、地方裁判所という司法裁判所の制度の中に組み込まれているものであるといえます。
また、不服があれば、裁判官だけで判決をする高等裁判所・最高裁判所で審理してもらえます。
従って、裁判員裁判は、司法裁判所の系列の外に置かれているものではなく、「特別裁判所」にはあたらないということです。